大阪府の株式会社きらくさまは1972年に創業され、”日常生活に密着した食文化への貢献”をモットーに「とんかつ」「らーめん」「うどん」「お好み焼き」「鶏」「中華」「カフェ」の7業種のレストラン事業を展開、現在では関西を中心に70店舗以上を経営されています。
このたび、GMOおみせアプリにて、効果的な情報発信で店舗認知度を向上させるため「きらく」公式アプリを制作されました。今回は、ご担当の中田さまにお話をお伺いしました。
- アプリプラン:エンタープライズ04(旧プラン)
- 利用開始:2020年3月
デジタル化が進んでいなかった
- ホームページがスマホ未対応
- 飲食系ポータルサイトに顧客が流れていた
- 飲食店の多くがアプリを導入
価格と充実した機能が決め手
- 予算的に一から作るのは難しい
- ニュース更新やクーポン配布機能が充実
- GMOおみせアプリを使っていた方から紹介
ダウンロードやクーポン利用も順調
- 2か月で10,000ダウンロード
- 月に約400回のクーポン利用
- 今後はスタンプラリーを開催予定
導入目的
- スマホ時代に対応する販促ツールを使って情報配信を行いたい
- 会社や店舗をまとめて紹介したい
機能について
- 各店舗の豊富なメニューをアプリで紹介
- アプリからECへのスムーズな誘導
- 近くにある運営店舗の検索が可能
中田様の業務内容についてお伺いできますか?
中田さま:
デザイン全般の業務をメインで行っています。
アプリに関すること以外でも、店内に設置するPOPを作ったり、卓上システムの画像作り込みなども行っています。
Q.アプリ導入に興味を持たれたきっかけについて教えてください。
中田さま:
「きらく」という会社を知ってもらうためのアプリを作りたい、そして弊社の飲食店7業種を1つのアプリにしたいということが始まりでした。
スマホもだいぶ普及している中でホームページがスマホ対応になっていなかったことや、弊社のホームページにはメニューの表示がありませんでした。
これまではお客様が飲食系ポータルサイトなどで調べていただいていたと思うのですが、そういった情報もこちらから発信しないといけない、今のままではもったいない、ということでアプリを検討し始めました。
また、いろいろな飲食店でアプリが導入されている中で、「もうアプリがないのはおかしいのではないか?」という意見もありました。
導入の目的としては、より多くのお客様へ他業態のお店を知っていただきたかったこと、また便利でお得な情報をお届けし、より楽しんでご利用いただけることを目指しました。
また、ニュース配信、プッシュ通知、メニューや店舗情報を載せることで、お客様への認知、リピート率の向上を目指しました。

これまではどのように集客・販促などを行われていましたか?
中田さま:
FacebookやInstagramなどのSNSで情報配信は行っていましたが、メルマガなどの配信はしていませんでした。
業務自体を少人数でやっていることもあり、したくてもできていないところがありました。
アプリは管理画面で開封率がすぐに確認できるので、よりわかりやすくなった感じがあります。
アプリの効果についてはまだ詳しくまでは分析ができていませんが、効果は感じ始めています。
Q.アプリの機能の中で、特に役立っていると感じる機能を教えてください。
中田さま:
ニュース機能です。
コロナ時もそうでしたが、ピンポイントな情報をすぐに配信することができ、また開封率も分かるので後の分析に繋がると感じています。
71店舗と店舗数が多いのですが、すでに全店舗での運用は開始されているのでしょうか?
中田さま:
71店舗すべての店舗でアプリのご案内に関する導入は完了している状態です。
アプリにメニューなどの情報が入っており、クーポンも業態別に月に1~2回配信しています。
店舗がたくさんありますが、アプリ運用開始時に準備したことなどはありますか?
中田さま:
スムーズに運用を開始できるように、いろいろ準備はおこないました。
アプリのボタン機能などについて説明した資料を作って各店舗に配布したり、お客様対応に関するマニュアルもあらかじめ準備しました。
店内にアプリをご紹介する販促物などは設置されましたか?

中田さま:
テーブルの上に置く三角POPを作りました。
アプリリリース段階では、レジ前にB5サイズくらいのリリースご案内POPを置き、QRコードを入れてアプリダウンロードの促進を行いました。
また、リリースから1ヶ月間、アプリインストール時に10%オフのインストールクーポンが自動発行されるようにしていました。
アプリ導入前に不安だったこと、大変だったことはありますか?
中田さま:
はじめは、1つのアプリの中にまとめないといけない業態が多いので、それをどういう風にまとめるのか、というのが考えどころでした。
ひとつの業態だけで出せるのであればその業態のことだけを考えればよいのですが、たくさんの業態の店舗をひとまとめだと、本当に何から手を付けていいのか分からない状態でした。
現場に関しても、導入当初はアプリに対して抵抗のある人もいました。
社員さんやパート、アルバイトさんなどさまざまな年代や立場の人たちが一緒に働いていますが、苦手意識のある方は少なからずおられました。
こちらではすぐに分かる、すでに理解していることでも現場では分からないということが多くあり、「まとめる」ということが課題でしたね。
また、ほかの社員さんに理解してもらうということも課題のひとつでした。
社内で使っているチャットでアプリについて告知したり、会議でアプリ運用についての段取りなどに関する説明も行いました。
やはり、はじめの一歩がなんでも大変なんですね。
中田さま:
アプリリリース直後は、お店の方から機能に関するお問い合わせの電話がよくかかってきました。
同じ説明を違う方に何度もしないといけないこともあり、メニュー更新作業なども重なって、71店舗を一人で管理するのが一番大変でした。
ただ、慣れてしまえば楽というか、そのうちにアプリでいろいろなことができるなと思うようになりました。
現場の方たちも慣れてくると「これをアプリでできないかな?」という風に聞いてきたり、「これをニュースで配信してほしい」などの要望も出てくるようになりました。
最初は大変でも慣れてしまえばこういう感じなのかというのを実感し始めています。
現場でも実際の業務の中で使えることが分かってもらえたことで、全体的にうまく流れるようになってきたと感じています。

たくさんあるアプリの中から「GMOおみせアプリ」に決めた理由を教えてください。
中田さま:
初めての試みで、当初は他の制作会社も調べていましたが、最終的に予算内で収まること、ニュース更新やクーポン配布など内容が充実していたことが決め手になりました。
検討中は他社さんと相見積もりも取りましたが、一から作るタイプだと2~3倍かかるのが分かりました。
期間がかかったり、金額もかなりあがるだけでなく、本当に一からの制作なので、何が必要で何が不要なのかというのを自分たちで決めないといけないというのは正直大変だと思いました。
予算的に一から作るのは難しいとなった時に、GMOおみせアプリを使っていた方から紹介してもらい、相談させていただきました。
確かに、検討している段階で、何があって何がないのかがはっきり分からない状態で、自分たちで仕様を決めていくのはなかなかハードルが高いですよね。
中田さま:
一からの制作の場合だと、たくさん機能がありすぎて困りますし、何があるのか分からないので必要なものを選びにくいこともありました。また、後から仕様を変えると大きな金額がかかることも理解していたので、その点も考慮しました。
本当に手探り状態でしたので、GMOおみせアプリには「パッケージ」があって、その点はとても安心でした。
また、担当者の方が打ち合わせに来てくれて、本当に細かく丁寧に教えてもらえたので、とても助かりました。
今年の2月に導入されたばかりですが、現在までのご感想をお伺いできますでしょうか?
中田さま:
2月、3月でダウンロードは順調で、現在ではすでに10,000ダウンロードを超えました。
コロナの影響で4月は一旦落ちましたが、ダウンロード数も戻ってきている状況です。
お店のほうも忙しいという声も聞かれるようになってきました。
自粛で外出されていなかったので、その反動で来店されていたり、常連さんが帰ってきてくださっているという現状です。
7月からは期間限定ではありますが、スタンプも活用する予定です。とんかつ店とラーメン店など、業態が違っていても、エリア的に密集しているお店もあるので、全店でどこに行ってもスタンプを貯められるようにするスタンプラリーのようなものを開催予定です。
実際にアプリを導入されて、既に効果を感じていらっしゃることは何かありますか?
中田さま:
クーポンを配信する際は、現場の担当とクーポン内容に関して打ち合わせを行い、配信しています。
お客様からは思っていたより反響がありました。
業態別のクーポンの使用数を分析してみたところ、月に400くらいは使われているのが分かり、その部分はとても安心しました。
クーポンを出してみて反応が悪い、逆に出すぎてお店を圧迫するかもしれないなど、実際にやってみないと分からないところが多かったので、現時点では月ごとに配信する形をとっています。
配信したクーポンの期限が過ぎたら新しいものを配信しているので、月に1~2回配信するという作業が発生します。
忘れたら大変なので、そのあたりは頑張っています。
最後に、アプリ導入を検討されている方に率直なメッセージをお願いできますか?
中田さま:
現場と距離が遠いほど意思疎通がしにくいと思いますので、そこはあらかじめ意思疎通をしっかり取っておくと実際の運用の際に役立つと思います。
また、アプリを入れて終わりではないので、運用を担当する人がいろいろな仕事を持っていると手が付かない時期が出てしまうこともあると思います。
アプリの運用を開始する前に、例えば効果測定をどのようにするのか、実際にどういった運用をしていくのかについてイメージしておくとよいと思います。
システム的なものをあらかじめ作っておくというのも大切ではないかと思います。私自身も、導入前に「この時期にこの販促があるからこのニュースを配信しよう」という年間スケジュールを立てました。
管理する店舗数が多くなればなるほどその部分が重要になるのではないかと思います。

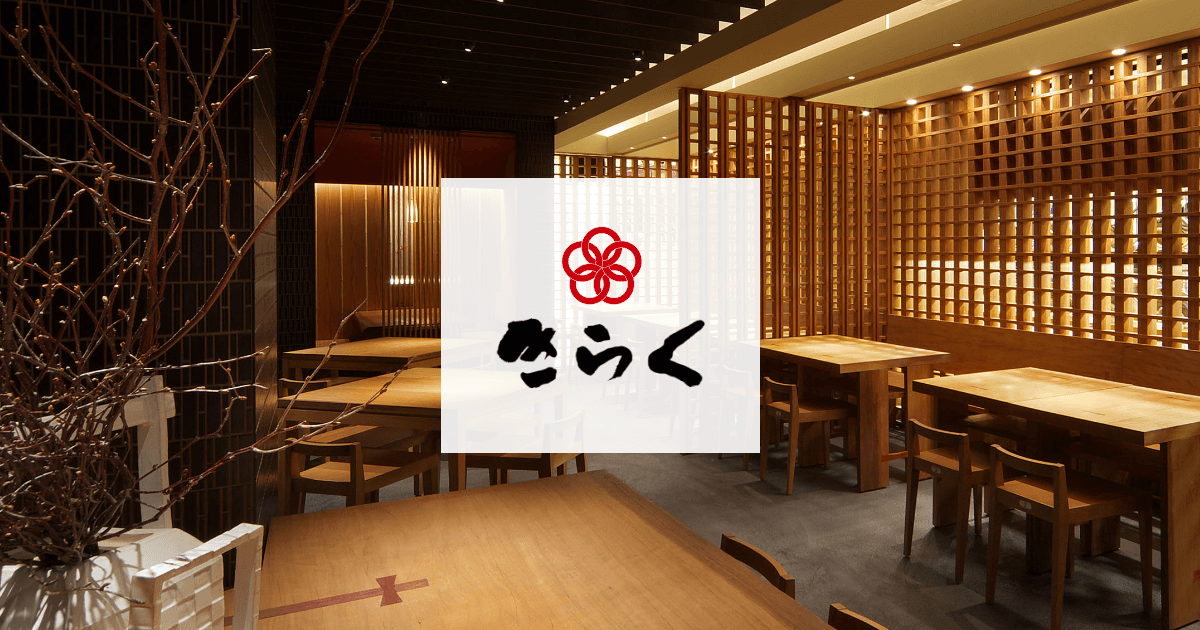
\ アプリ活用のヒントが多数掲載 /



