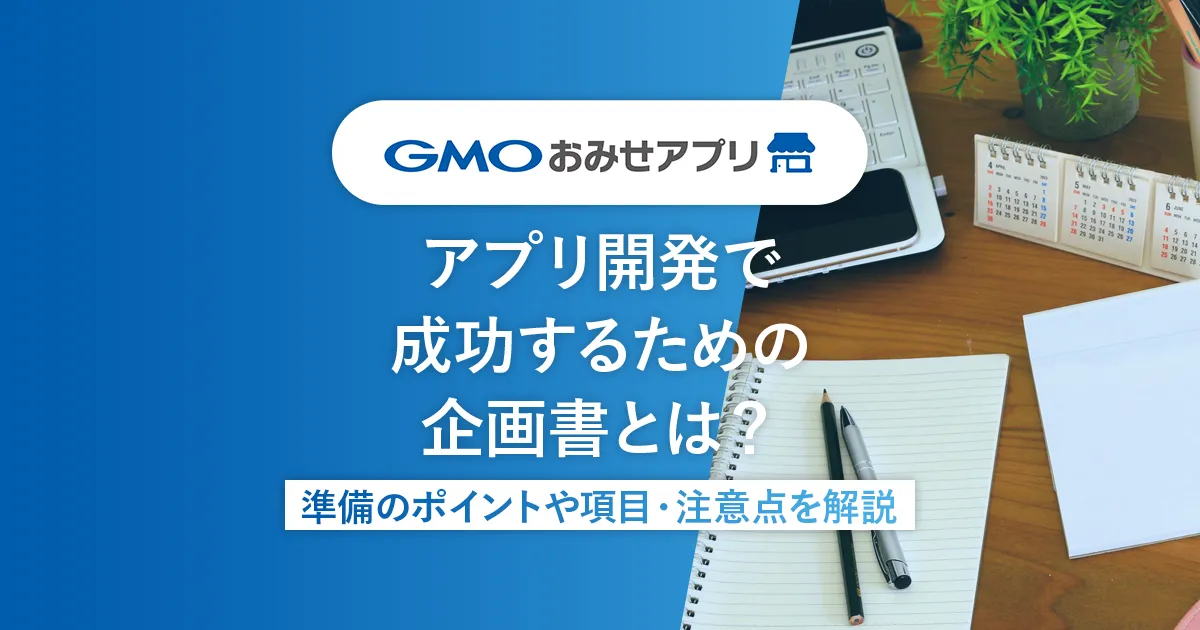アプリ開発を成功させるためには、明確な企画書の作成が欠かせません。
アプリ開発における企画書の役割
社内での合意を促せる
アプリ開発は、自部署のみで完結する業務ではありません。アプリ開発をスムーズに進めるためには、社内のさまざまな部署において理解や協力が不可欠です。アプリ開発の企画書を作成することで、アプリ開発の必要性やスケジュールなどを事前に理解してもらいやすくなり、スムーズに合意、協力が得られるでしょう。
アプリ開発の方向性を常に確認できる
アプリ開発は、工程を進めるなかで作業に追われることも少なくありません。アプリ開発そのものが目的化して、本来の目的を見失うことも考えられます。アプリ開発は、企画書をもとに、常に現在の立ち位置や方向性を確認し、本来の目的からずれたり、方向性が間違っていたりしないかを確認することが重要です。
アプリ開発の企画書準備のポイント
アプリ開発の企画書を作成する際は、目的やターゲットを明確にし、事前に競合を調査しておきましょう。ここでは、企画書を準備する際に意識すべき3つのポイントを解説します。
アプリ開発の目的を明確にしておく
アプリ開発の企画書を作成する際は、何のためにアプリを開発するのかを明確にしましょう。アプリによって解決したい課題を言語化することで、プロジェクトメンバー間での齟齬を防げます。また、課題をアプリで解決する必要があるかについても、自問自答することが重要です。アプリ開発の先にあるゴールを見据えたアプリ開発の準備が求められます。
ターゲットを明確にしておく
アプリ開発の目的を決めたら、続いて、ターゲットを明確にします。開発したアプリを利用してほしいターゲットを細かく設定していきましょう。ターゲットが何に悩んでいるのか、解決したい課題は何か、どのようなニーズがあるのか、ユーザーの深層心理や行動の動機を深堀りしましょう。ターゲットを明確にする方法として、ペルソナやカスタマージャーニーの設計も有効です。
競合を調査する
ターゲットを明確にしたら、最後に自社の競合企業が導入しているアプリについて調査します。競合他社のアプリが搭載している機能や発信しているコンテンツ、アプリの告知方法などを調査しましょう。あわせて、インターネット上やアプリストアにあるレビューも確認します。
アプリ開発で最初に決めるべき3つの項目
アプリ開発を進める際は、まず、以下の3つを先に決めておく必要があります。
- アプリのタイプ
- 対応プラットフォーム・デバイス
- 実装する機能
それぞれの選定ポイントを解説します。
アプリのタイプ
アプリのタイプは、大きくネイティブアプリとWebアプリに分かれます。ネイティブアプリとは、App StoreやGoogle Playといった、アプリストアからダウンロードして利用するアプリです。Webアプリは、アプリストアからダウンロードせずにWebブラウザ上から利用可能です。
一般的に、「アプリ」とのみ記載されている場合は、ネイティブアプリを指します。ネイティブアプリとWebアプリは、それぞれ長所と短所があります。それぞれの特徴や強みと、自社がアプリを導入する目的を鑑みて、状況にあったアプリのタイプを選ぶことが大切です。
対応プラットフォーム・デバイス
ネイティブアプリを開発する場合、対応するプラットフォームを決めなければなりません。iOSアプリとAndroidアプリそれぞれで、開発環境が異なります。iOS端末に対応させるか、Android端末に対応させるか、あるいは両方に対応させるかによって開発にかかる費用や時間などのコストが異なります。
あわせて、アプリに対応するデバイスの範囲も決めなければなりません。デバイスの対応範囲が広がるほど、予算や開発の工数がかさみます。
実装する機能
ターゲットとなるユーザーの目線に立って、アプリに実装する機能を選びましょう。ユーザーがどのような機能を欲しているか、どのような機能があったら便利かといった視点で選定することが重要です。アプリに実装する機能が多すぎると、予算がかさむばかりか、オーバースペックになり、ユーザーが使いにくいと感じる可能性が高まります。
アプリは、段階的に機能を追加したり、改善したりするスタイルが主流です。選定した機能をさらに厳選し、まずは最低限の機能を実装したアプリをリリースしましょう。
アプリ開発の企画書に盛り込む基本的な項目
アプリ開発では、最初に決めるべき3つの項目のほか、企画書に盛り込むべき基本的項目があります。ここでは、7つの基本項目について解説します。
デザイン
アプリはユーザーが使いやすく、興味を引くデザインを目指しましょう。どれだけ魅力的なアプリであっても、デザインが期待外れだと、ユーザーが興味や関心を失いかねません。ブランドイメージやターゲットの好みを加味して、アプリのカラーやフォント、アイコンのスタイル、画面レイアウトなどを決めましょう。
容量の目安
アプリ開発の際は、アプリの目安となる容量も設定しましょう。決定した容量を目安に、開発段階で容量の最適化やストレージ管理に取り組みます。アプリの容量が大きすぎると、ユーザーがダウンロードを躊躇してしまい、離脱につながりかねません。競合他社の容量を確認し、適正な値を設定しましょう。
マネタイズ戦略
アプリ開発では、マネタイズの戦略についても企画書に詳細に記載しておく必要があります。アプリを開発、リリースすることで自社の売り上げにどのように貢献できるかを明確化します。なお、売り上げに貢献する方法は、アプリ内課金、広告表示、アプリを通した自社サービスの利用など多岐にわたります。アプリを含めたマーケティング施策を検討しましょう。
スケジュール
アプリの開発には、要件定義、デザイン、開発など複数のステップを踏まなければなりません。各フェーズの期間やマイルストーンを設定し、細かなスケジュールを設定します。アプリ開発の企画書作成段階でスケジュールを明確にしておくことで、開発プロセスを俯瞰して把握できます。
開発費用
実装する機能や開発する方法などにより、差はありますがアプリ開発には費用がかかります。企画書には、アプリ開発で想定される費用をできるだけ細かく記載しましょう。デザイン料や人件費、ツールやライセンスの使用料など、項目ごとに細かく予算を算出し、記載します。これにより、予算管理や資金調達がスムーズに進められるでしょう。
リリース後のプロモーション
アプリをリリースした後、できるだけ多くのユーザーにアプリを活用してもらうためには、プロモーション施策が重要です。アプリはユーザーにダウンロードしてもらい、使われなければ意味がありません。SNSの活用、広告施策、クーポン配布、キャンペーン実施などのプロモーションに積極的に取り組み、自社アプリの認知度を高めましょう。
アプリを評価するための指標
アプリは作って終わりではなく、パフォーマンスを評価し、前述した通り改善や戦略の見直しをすすめなければなりません。評価指標を決める際は、KGIとKPIを分けて考えます。アプリ開発においてKGIは、商品の売り上げや有料会員数、具体的な利益などです。KPIは、KGIの達成のために必要な要件で、ダウンロード数や利用率などがこれにあたります。
企画書段階で確認すべきアプリ開発における注意点
アプリ開発では、注意すべき点がいくつかあります。ここでは、企画書段階で確認すべき注意点について解説します。
著作権侵害に注意する
前述の通り、アプリ開発では競合他社のアプリを調査・分析することが重要です。ただし、他社アプリを参考にする際は、単なる模倣に留まらず、自社の独自性を加えて差別化を図る必要があります。
なお、アプリの機能や操作フロー自体は著作権の対象ではありませんが、画面デザインやUI構成が独創的なものである場合、それをそっくり真似ると著作権侵害や不正競争防止法に抵触するおそれがあります。過度な模倣はリスクを伴うため、他社との差別化とオリジナリティの確保が重要です。
また、アプリ内で使用する画像、音声、フォント、テキストなどのコンテンツについても著作権に十分注意が必要です。使用する素材は、必ず以下のいずれかに該当することを確認しましょう。
- ライセンスを正当に取得しているもの
- 著作権フリー(パブリックドメインまたはCC0など)で明示的に商用利用可とされているもの
- 著作権者から許可を得たもの
さらに、自社で撮影・制作した素材であっても、人物が特定できる形で写っている場合は肖像権の問題が生じます。被写体本人の許諾を得るか、モザイク処理などで個人を特定できないようにする配慮が必要です。撮影時には不特定多数の人が映り込まない場所を選ぶなど、事前の対策を講じましょう。
法的事項を確認する
アプリ開発では、著作権法のほかにも、法的な観点から確認するべきことがあります。例として、以下が挙げられます。
- プライバシーポリシー
- 利用規約
- 個人情報の取り扱い
とくに、個人情報の取り扱いは慎重に行いましょう。法的事項に関する確認や対策は事前に進め、法的なリスクを回避しましょう。
まとめ
アプリ開発で企画書を作成することで、社内でのアプリ開発の理解、協力につながり、方向性を失わずに開発を進められるようになります。
弊社の店舗アプリ制作サービス「GMOおみせアプリ」は、2025年5月時点で、3,220社/11,100店舗の導入実績があります。高品質かつコストパフォーマンスに優れたアプリを提供し、さまざまな業種の企業や店舗様にご利用いただいております。
GMOおみせアプリは、充実したカスタマーサクセスで3,220社/1万1,100店舗の導入実績があります。ノーコード系のアプリ開発ルールと異なり、おまかせでアプリ制作が可能です。外部システムとも柔軟にAPI連携が可能で、業務効率化にもつながります。詳しくは、資料請求、お問い合わせください。