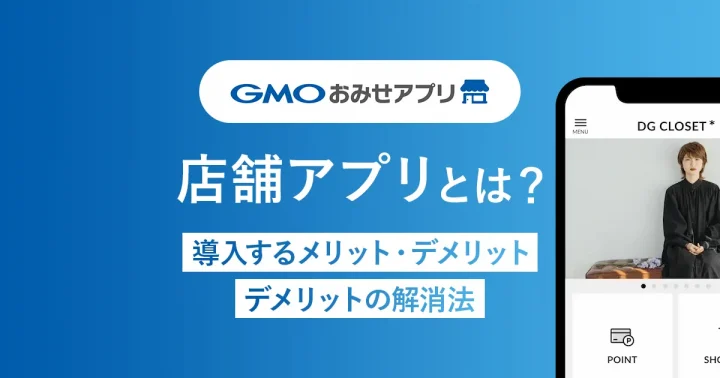OMO(Online Merges with Offline)とは、オンラインとオフラインの融合を意味します。
企業が利益を増やしたいと考えた時、まず始めに新規出店を検討することが多いでしょう。しかし近年IT技術の発達により、店舗アプリを導入しOMOに投資することで、新規出店をすることなく利益を増やすことも可能になりました。
OMOとは?
OMOとは、オフラインとオンラインの境界を取り除き、ひとつのものと捉えるマーケティング戦略の一種です。
すでに多くの企業が、このOMOを導入しています。店舗においては、オフライン・オンラインに関係なく複数のチャネルとして運営しながら、自社製品・サービスのPR活動と販売を行っています。
中国におけるOMOの進化
2020年以降コロナ禍によって、実店舗の販促が滞り、オフラインの見直しとして国内外にかかわらずOMO化が進みました。
特に中国は、世界に先駆けて最もOMOを発達させている国です。中国の都市部では、ショッピングをする際にスマートフォンを使った決済が当たり前になっています。
このスマホ決済は、顧客にとって便利なだけではなく、企業側にも大きなメリットがあります。それは、今まで別々で行っていたオフラインとオンラインの顧客の行動分析や管理などを一元化できることです。
中国ではOMOの導入による、精密な顧客の行動データを使ったマーケティング戦略が近年の主流になっています。
OMO・O2O・オムニチャネルといった似ている概念を整理
OMO(Online Merges with Offline)、O2O(Online to Offline)、およびオムニチャンネルの比較表です。これらのマーケティング戦略は、オンラインとオフラインの統合を促進し、顧客体験を向上させることを目的としていますが、それぞれの特徴に違いがあります。
| 特徴 | OMO | O2O | オムニチャンネル |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | オフラインとオンラインの融合 | オンラインからオフラインへ誘導、またはオフラインからオンラインへの誘導 | すべての経路の活用 |
| オフライン重視か | 一部の戦略でオフライン重視 | オフラインを重視しながら、オンラインと関連を持たせる | すべての経路平等 |
| 主軸 | 購買体験 | オフライン購買 | 顧客の購買行動 |
| オンラインとオフラインの区別 | 一部の戦略で区別なし | 区別あり | 区別なし |
| 例 | オンラインでの情報提供、店舗内デジタル技術の活用 | オンラインクーポン、ウェブ予約 | ウェブ・アプリ・実店舗のシームレスな体験 |
簡単にまとめると、OMOはオフラインとオンラインの融合を通じて購買体験を向上させる戦略で、O2Oはオンラインからオフラインへの誘導(またはその逆)を中心に据えた戦略です。
一方、オムニチャンネルはすべての経路を活用して顧客の購買行動を支援する戦略で、オンラインとオフラインの区別をあまり強調せず、顧客の利便性と体験を最優先に考えます。


OMO化がもたらすメリット
OMO化することで得られるメリットを2つ解説します。
LTVの最大化
顧客の購入体験が向上すると、多くの顧客が自社のリピーターになる可能性があります。リピーターが増えれば、より多くの商品を自社で購入する顧客が増加して、自社の継続的な利益につながります。
真のニーズの発見
OMOに対応することで、顧客が持つ真のニーズを発見できます。
真のニーズを把握することで、顧客に合わせたおすすめの商品・サービスの表示が可能となり、顧客の購入体験をさらに向上できます。
OMO戦略を成功させるためのポイント
OMOによるマーケティング戦略を成功させるためのポイントについて解説します。
良質な顧客体験をデザインする
OMO戦略を成功させるためには、その顧客体験をより良質なものへとデザインしなければなりません。
良質な顧客体験をデザインするためには、顧客の視点に立って考察することから始めることがポイントです。その際、自社が現在提供しているサービスや他のサービスに対して、以下の点を確認しながら進めましょう。
- 不足しているものは何か
- その不足は補えるか
- それは補う必要があるか
これらを明確化することで、良質なデザインを作ることができます。
顧客との接点を増やす
OMO戦略においては、できるだけ多くのデータを集めることが鍵となります。
顧客データを一元管理する
その膨大なデータの保管先として、安価で扱えるクラウドストレージを採用することも効果的です。すでに自社システムの各所にデータが保管されている場合は、データの統合が重要課題となります。複数のチャネルでのデータを集計・連携させるツールを活用して、顧客データの一元管理を進めましょう。
OMO専任担当者を置く
そのため、各チャネルやICTの知識だけではなく、それらのチャネルを横断してデータを活用する方法や、オンラインをどのように活用して課題を解決するかという視点を持った担当者が必要です。
もちろん、担当者には複数の部門との連携が求められます。そのため、社内でのデータ連携ができる仕組みを構築することも欠かせません。

BOPISによるOMOの事例紹介
マクドナルドのモバイルオーダーの事例
スムーズな注文と受取
マクドナルドのモバイルオーダーは、スマホを使って自宅から商品を注文し、店舗で受け取る革新的な取り組みです。これにより、顧客は出来上がる頃に合わせて店舗に向かい、待ち時間がなくなる利便性を享受できます。
注文オプションの多様性
顧客はテイクアウトか店内での食事かを選択できるだけでなく、店内の席まで商品が運ばれるオプションもあります。事前決済により、混雑時でもスムーズに受取可能。
顧客の利便性向上と売上増加
マクドナルドの取り組みは、顧客の利便性を最優先に考えたサービス提供によって、購買回数の増加と売上の伸びを実現しています。
ファッションセンターしまむらのオンラインストアの事例
主婦層に配慮したオンラインストア
しまむらは主婦を中心とした購買層を持ち、店舗への足が遠のく声に応えて、幅広い商品を提供するオンラインストアを展開。実店舗にはないオンライン限定商品も用意。
BOPISによるコスト削減と利便性向上
しまむらはオンラインで購入した商品を実店舗で受け取る「BOPIS」を導入。送料節約のメリットと合わせて、実店舗で他の商品も購入しやすい環境を提供し、顧客満足度と売上向上に貢献。
ホームデポのアプリの事例
ペイント選びの革新
ホームデポのアプリは、ペンキ選びを助ける機能を提供。写真から色を選び、イメージ画像を表示して後悔を減少。在庫確認や取り寄せも可能で、顧客の選択を支援。
便利な店舗アプリの役割
ホームデポは店舗アプリを通じて顧客の利便性を向上。在庫の確認や効率的な商品選択により、店舗とオンラインの利用を促進し、売上増に貢献。
アリババのスーパーの事例
フーマフレッシュの顧客魅力
アリババが運営するフーマフレッシュは、OMO化に注力。アプリでまとめて購入や即日配送が可能。また、魚のQRコードや運搬過程の情報提供により、顧客の興味と信頼を高めています。
アプリによる全決済データ把握
アプリを通じた全決済により、アリババは購買データを収集。経営戦略の最適化に役立てつつ、顧客の利便性向上と企業の効率化を実現しています。
OMO化のために店舗アプリを導入しよう
店舗アプリはモバイルオーダー機能だけでなく、クーポンの配布などもできて顧客にとってのメリットが大きく、満足度の上昇が期待できます。
また、顧客の利用状況や購入履歴などが分析できて、効率的に集客効果を上げることもできるでしょう。OMOに課題をお持ちの場合は、店舗アプリの導入を検討してみてください。
弊社の店舗アプリ制作サービス「GMOおみせアプリ」は、2025年5月時点で、3,220社/11,100店舗の導入実績があります。高品質かつコストパフォーマンスに優れたアプリを提供し、さまざまな業種の企業や店舗様にご利用いただいております。